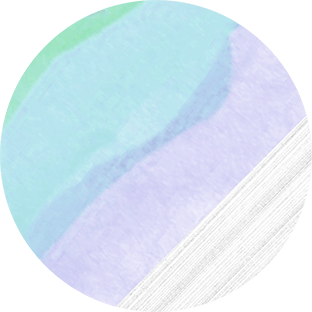祈りのように眩しい
文月 悠光
町の本屋さんで見た、ある光景が目に焼きついている。二〇代後半と思しき男性が、文芸誌を開いたまま、黙って横の女性に差し出した。一旦本を閉じてしまっては、文字が消えてしまうかのように、自分の感じたものをページの上に乗せ、静かに彼女へ運んでみせた。
彼女もそれを両手で黙って受け取り、しんしんと読んでいた。互いに目を合わせる様子もない。それでも、二人の心が通い合っていることがよく伝わってきた。
それは冬の夜だった。冷たい彼女の手に、ページの触れる音が聞こえるようで、私はハッと胸を掴まれた。自分もそのように言葉を手渡したい、手渡されたいのだ、と書棚の陰で気がついた。
もし本を渡すそのとき、彼が得意げに表紙を見せながら、「この作者はね……」とうんちくを語り出したら、ゲゲ、最悪だ。もちろん、知識を得る歓びによって書物が読まれ、文化が支えられる側面はあるけれど。彼が黙って本を差し出したとき、そこで手渡されたのは、単なる〈情報〉でも、「自分の力を認めさせたい」という身勝手な〈欲望〉でもなかった。
サン=テグジュペリが綴った「愛とは、見つめ合うことではない。ふたりが同じ方向を見つめることである」という有名な文句を図らずも思い出した。彼は、彼女の見つめる場所を知っていた。だから、彼女の見る景色にふさわしい本を、双眼鏡のように手渡したのだ。
出版するために編集することを「本を編む」と呼ぶ人がいる。不思議な表現だ。本を読むとき、私たちはテキストの織物を両手に広げ、書き手の編んだ道筋を地図のように辿っていく。その導きに心地よく身を任せたり、ときに首をかしげたりしながら。
親密になりはじめた二人(男女とは限らない)が本を貸し借りするのは、相手と同じ道筋を歩いてみたい、という希望の表れなのだろう。そうすれば互いにわかり合える気がして。
同じ道を歩いても、それぞれ目を向けるものが全く違うように、それは永遠に達成されない願いなのだけれど。
電車の中で編み物をしている女性を見たことがある。彼女は前の優先席には腰掛けず、揺られながら両足でバランスを取り、編み棒を動かし続けていた。「立ったまま編む」という姿勢は、彼女の譲れない哲学のようだった。
彼女の指が、モスグリーン色の毛糸を持ち上げては、編み棒へと引っ掛ける。手つきはひどく不慣れで、だからこそ、全神経が手元に集中していた。〈祈り〉のような、ひどく眩しい光景だった。
彼女は誰のためでもなく、自分のために「編む」ことを繰り返していた。仮に、誰かの誕生日や記念日に間に合わせるためだったとしても、さして関係はない。私は彼女の姿に、自分自身をも編み込んでいく〈気迫〉を感じた。「編む」ことは、たとえば神のような、遠くの存在と交信する儀式のようだ。
実際、その手元で行われているミクロな運動は、宇宙的な世界に繋がっている。なぜなら、彼女が手を動かさなければ、毛糸は毛糸のまま。編み物にはならない。彼女はいわば創造主だ。
頭を打ったとき、咄嗟に自分の頭に手を当てる。痛みに手をあてがい、内に抱え込むような姿勢を取る。手の動作が魅力的なのは、そこに「痛み」があるように見えるからだろうか。か弱く、守るべき核心が、その手の中に秘められている。
片手間ではなく、しっかり両手を捧げている人に出会うと、私はつい胸が熱くなる。
一心に「編む」こと。ある方向を見つめている誰かに、それを「手渡す」こと――。言葉に関わる人間として、私は二つの光景を決して忘れないだろう。この手で一生かけて守っていきたい。
(初出:東京新聞夕刊2016年10月6日)
メディアに寄稿した詩やエッセイのうち、
書籍未収録の作品を一部掲載しております。